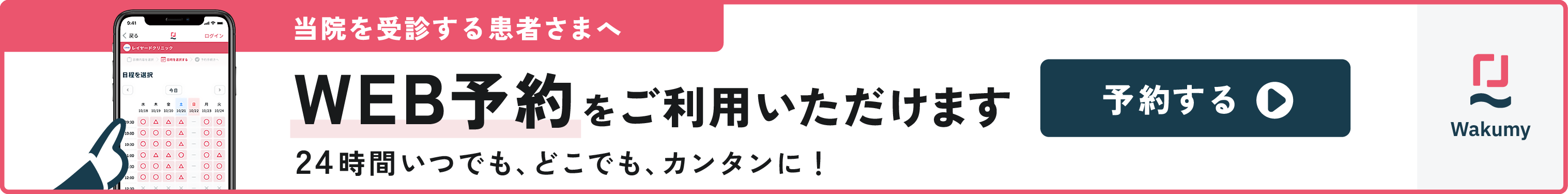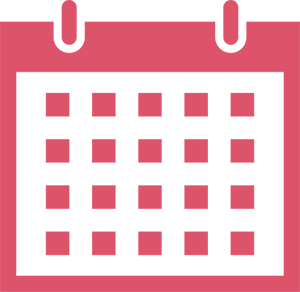長引く咳
江東区で長引く咳にお悩みの方へ

咳は通常、風邪症候群やインフルエンザなどの呼吸器感染症の場合、2~3週間すれば治まります。
3週間以上続く咳を「遷延性の咳」、さらに長引く咳で8週間以上続いている咳を「慢性の咳」と言います。咳が長引けば長引くほど、感染症以外が原因となっている可能性が高くなります。
こうした場合に何が疑われるのかと言えば、可能性として高いのは、やはり呼吸器疾患です。呼吸器の疾患は咳が出ることが多く、急性咳嗽とされる期間よりも長引く咳嗽に関しては、早めの受診から、適切な検査、診断を行い、治療していく事が大切です。
ただし、咳の3大原因は、SBS(副鼻腔気管支症候群)、GERD(胃食道逆流症)、CVA(咳喘息)と言われており、呼吸器疾患以外の鑑別も重要になってきます。
当院では、鑑別診断をきちんと行い、適切な診断に基づいた治療を行なっています。
咳が止まらずお悩みの方は、ぜひ一度ご受診ください。
また、漫然と治療されている方も、一度当院へ診断についてご相談ください。
治療継続の必要性も一緒に考えていきます。
咳の原因となる疾患
咳の原因となる疾患は、「咳がどのくらい続いているか」や「痰(たん)が出るかどうか」などによって推定していきます。原因疾患を特定することで効果的な治療ができます。
- 3週間未満の咳(急性咳嗽)
痰あり・・・風邪、急性気管支炎、肺炎などの急性炎症、気道異物
痰なし・・・急性気管支炎などの急性炎症 - 3週間以上8週間未満の咳(遷延性咳嗽)
痰あり/痰なし・・・マイコプラズマ肺炎、百日咳、肺炎クラミジアなど
- 8週間以上の咳(慢性咳嗽)
痰あり・・・気管支ぜんそく、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支拡張症、副鼻腔気管支炎など
痰なし・・・咳ぜんそく、アトピー咳嗽(アレルギーによる咳)、逆流性食道炎、副鼻腔気管支炎、肺結核、肺がん、心因性など
3週間未満の咳(急性咳嗽)
咳が発症してから3週間以内におさまるものを「急性咳嗽(きゅうせいがいそう)」と呼びます。多くの場合、ウイルスや細菌による呼吸器系の感染症が原因となりますが、異物の吸入などによって引き起こされることもあります。発熱、鼻水、喉の痛みといった他の症状を伴うことが一般的です。
- 風邪
- 風邪は、ライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルス、アデノウイルスなど、さまざまな種類のウイルスが鼻や喉などの上気道に感染することで起こる疾患です。
咳は風邪の主要な症状の一つであり、感染初期から現れることもあれば、他の症状が治まった後に咳だけが残ることもあります。通常、数日から2~3週間程度で自然に治癒しますが、咳が長引く場合や悪化する場合は、他の呼吸器疾患の可能性も考慮する必要があります。 - 急性気管支炎
- 急性気管支炎は、気管や気管支の粘膜に炎症が起こる疾患です。多くは風邪のウイルス感染が原因で、風邪に続いて発症することが一般的ですが、細菌感染によって引き起こされることもあります。
主な症状は、痰を伴う咳で、最初は乾いた咳でも次第に痰が絡む湿った咳に変わることが多いです。発熱や胸の不快感を伴うこともあります。
咳は数週間続くことがありますが、多くの場合、自然に治癒します。ただし、呼吸が苦しい、高熱が続くといった症状がある場合は、肺炎への移行も考えられるため注意が必要です。 - 気道異物
- 気道異物とは、食べ物(豆類、ナッツ、餅、飴など)や小さなおもちゃの部品などが誤って気管や気管支に入り込んでしまう状態を指します。特に乳幼児や高齢者に多く見られます。
気道に異物が入ると、体が異物を排出しようとして突然激しい咳き込みが起こります。これは生体防御反応の一つです。異物の大きさや場所によっては、呼吸困難、顔面蒼白、チアノーゼ(唇や爪が青くなること)などの症状が現れ、窒息につながる危険性もあります。
突然の激しい咳き込みや呼吸困難が見られる場合は、緊急で医療機関を受診する必要があります。
3週間以上8週間未満の咳(遷延性咳嗽)
咳が3週間以上8週間未満続く場合を「遷延性咳嗽」と呼びます。急性咳嗽が治まった後も咳が続く状態や、慢性咳嗽に移行する前の段階として見られることがあります。この期間の咳は、一般的な風邪が長引いていると誤解されがちですが、特定の疾患が原因となっている場合も少なくありません。
- マイコプラズマ肺炎
- マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマ・ニューモニエという細菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。主な症状は発熱、頭痛、全身倦怠感ですが、特徴的なのはしつこく続く乾いた咳です。
初期は比較的軽い咳ですが、次第に強くなり、夜間に悪化する傾向があります。小児から成人まで幅広い年齢層で発症し、集団感染することも少なくありません。
胸部X線検査で肺炎像が認められることもありますが、典型的な細菌性肺炎とは異なり、比較的軽症で経過することもあります。
診断には血液検査やPCR検査が用いられ、マクロライド系抗菌薬が治療に用いられます。 - 百日咳
- 百日咳は、百日咳菌によって引き起こされる細菌性の呼吸器感染症です。乳幼児期に予防接種を受けていない場合や、成人でワクチンの効果が薄れた場合に発症することがあります。
特徴的な症状は、激しい咳の発作です。初期は軽い風邪のような症状ですが、次第に咳がひどくなり、顔を真っ赤にして息を吸い込む際に「ヒュー」という笛のような音(吸気性笛声、フーピング)を伴うことがあります。咳の後に嘔吐することもあります。特に乳児では、咳き込みによる無呼吸発作やチアノーゼを起こすなど重症化するリスクもあります。
診断は、鼻咽頭からの検体採取や血液検査によって行われ、マクロライド系抗菌薬による治療が行われます。 - 肺炎クラミジア
- 肺炎クラミジア(Chlamydophila pneumoniae)は、クラミジアの一種で、呼吸器感染症の原因となります。この菌による感染症は、比較的軽度の発熱、咽頭痛、嗄声(声枯れ)といった症状から始まり、その後、乾いた咳が長期間続くことが特徴です。
マイコプラズマ肺炎と症状が似ているため、区別が難しい場合もあります。学童期から成人にかけてよく見られ、集団発生することもあります。
診断には血液検査やPCR検査が用いられ、マクロライド系抗菌薬やテトラサイクリン系抗菌薬が治療に用いられます。
8週間以上の咳(慢性咳嗽)
咳が8週間以上続く場合、「慢性咳嗽」と呼びます。この段階では、感染症以外の呼吸器疾患が原因となっている可能性が高くなってきます。
- 気管支拡張症
- 気管支拡張症は、肺の中の気管支が異常に拡張し、元に戻らなくなる病気です。拡張した部分には痰がたまりやすく、細菌感染を繰り返すことで、さらに気管支の壁が破壊されて拡張が進むという悪循環に陥ります。
主な症状は、慢性的に続く湿った咳と多量の痰です。痰は膿性で、時には血が混じることもあります。感染を繰り返すと発熱や倦怠感を伴うこともあります。過去の重症肺炎や結核、百日咳などの感染症が原因となることが多いですが、先天的な要因や免疫不全が関与している場合もあります。 診断には胸部レントゲンや胸部CT検査が重要となり、治療は感染に対する抗生物質の使用や、気道内の痰を排出するための理学療法などが中心となります。
- 副鼻腔気管支症候群
- 副鼻腔気管支症候群は、鼻の奥にある副鼻腔の炎症(副鼻腔炎、いわゆる蓄膿症)が原因で、気管支にも炎症が波及したり、鼻から喉へ流れ落ちる鼻水(後鼻漏)が気管支を刺激することで慢性的な咳が引き起こされる状態です。
症状としては、鼻水、鼻づまり、後鼻漏による喉の違和感や痰が絡む咳が特徴です。特に夜間や朝方に咳が悪化しやすい傾向があります。鼻の症状が先行することが多く、耳鼻咽喉科での診察や、副鼻腔のレントゲン検査やCT検査で診断されます。治療は副鼻腔炎の治療が中心となり、抗生物質や去痰薬、鼻洗浄などが行われます。
- 咳ぜんそく
- 咳ぜんそくは、気管支ぜんそくの一種ですが、典型的な喘鳴(ぜんめい:ヒューヒュー、ゼーゼーという呼吸音)や呼吸困難を伴わず、咳だけが唯一の症状として現れるタイプのぜんそくです。
主な症状は、乾いた咳が慢性的に続くことです。特に、夜間から早朝にかけて出やすくなります。運動後や冷たい空気に触れた時、会話中などにも咳が誘発されやすいのが特徴です。 風邪をひいた後に咳だけが長引くという形で発症することもあります。アレルギー体質の方に多く見られ、気道が過敏になっていることが原因です。気管支拡張薬が有効であることが診断基準の一つに含まれます。
- アトピー咳嗽
- アトピー咳嗽は、アレルギーが関与する慢性的な乾いた咳で、咳ぜんそくと症状は似ていますが異なる疾患です。咳ぜんそくに有効な気管支拡張薬が、アトピー咳嗽には効きません。
症状は、喉のイガイガ感や乾燥感、それに伴う乾いた咳が中心です。特定の刺激(冷気、会話、喫煙、特定の匂いなど)で咳が誘発されやすいですが、咳ぜんそくのような気道の狭窄は認められません。 アレルギー体質の方に多く、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎などを合併していることもあります。抗ヒスタミン薬が有効であることが多く、アレルギー検査で原因物質を特定することもあります。
- 逆流性食道炎
- 逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで、食道の粘膜が炎症を起こす病気です。この胃酸が喉や気管支まで逆流し、刺激することで慢性的な咳を引き起こすことがあります。
典型的な症状は、胸やけや呑酸(どんさん:酸っぱいものが口まで上がってくる感覚)ですが、咳だけが唯一の症状として現れることも少なくありません。食後や横になった時、前かがみになった時に咳が悪化しやすい傾向があります。咳は乾いた咳であることが多いです。 胃カメラ検査で食道の炎症を確認したり、胃酸を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)を服用して咳が改善するかどうかで診断されることがあります。
- 肺結核
- 肺結核は、結核菌という細菌が肺に感染することで起こる感染症です。かつては国民病として恐れられましたが、現在でも完全に撲滅されたわけではなく、高齢者を中心に新規の感染者が報告されています。
初期には自覚症状が少ないこともありますが、進行すると慢性的な咳(乾いた咳から湿った咳、時には血痰を伴うことも)、微熱、だるさ、寝汗、体重減少などの症状が現れます。
胸部レントゲン検査や喀痰検査(痰の中に結核菌がいるか調べる検査)で診断され、治療には複数の抗結核薬を長期間服用する必要があります。感染症であるため、周囲への感染拡大を防ぐことも重要です。 - 心因性咳嗽
- 心因性咳嗽は、身体的な病気が見当たらないにもかかわらず、精神的なストレスや心理的な要因が関与して咳が続く状態を指します。
特徴としては、日中活動している間は咳が出るものの、睡眠中は咳が完全に止まることが多い点が挙げられます。また、咳の音が特徴的で、「ワンワン」という犬の鳴き声のような音や、甲高い音がすることもあります。
身体的な原因がないことを確認した上で、咳を悪化させるストレスの軽減や生活習慣の改善が重要となります。必要に応じて鎮咳薬や抗不安薬が補助的に用いられることもあります。
当院で行っている咳の検査
上述の通り、咳は風邪などの一時的なものから、感染症、アレルギー、喘息、胃酸逆流、肺の気質的な病気などさまざまな原因で起こることがあります。
当院では、正確な診断のために、詳しい検査を行い、最適な治療方針を決定します。
-
問診・診察
咳の持続期間、どのような咳か(乾いた咳・痰を伴う咳)、発熱の有無、既往歴(過去にかかった病気)などを詳しくお伺いします。
-
血液検査
炎症の有無やアレルギー反応、感染症の可能性を確認します。
-
胸部レントゲン検査
肺炎や結核、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や器質的疾患(肺や気道そのものの炎症や癌)などの異常がないかを確認します。
-
呼吸機能検査
喘息やCOPDの可能性を調べるために、肺の機能を測定します。 当院では、呼吸器の専門クリニックとして、呼気NO検査や、総合呼吸抵抗測定装置モストグラフといった検査機器もあります。
・呼気NO検査とは?
呼気(吐いた息)に含まれるNO(一酸化窒素)の量を測る検査で、気道の炎症の程度を調べます。特に喘息の診断や治療効果の評価に役立ちます。簡単な検査で、痛みもなく、短時間で結果が出ます。
・総合呼吸抵抗測定装置モストグラフとは?
呼吸の抵抗(空気の通りやすさ)を測定し、気道が狭くなっているかを調べます。通常の肺機能検査では分かりにくい小さな気道の異常も検出可能です。早期の喘息やCOPD・気管支炎の発見に役立ちます。マウスピースをくわえて、数十秒間自然に呼吸するだけで測定できるため、通常の肺機能検査が難しい方(小児や高齢の方)でも受けやすい検査です。 -
喀痰検査 (必要に応じて)
細菌や結核菌などの感染を確認するために行います。
-
アレルギー検査 (必要に応じて)
アレルギーが関与している可能性がある場合、血液検査や皮膚テストを実施します。
-
胃酸逆流(GERD)の評価 (必要に応じて)
逆流性食道炎が咳の原因となることがあるため、症状に応じて評価します。